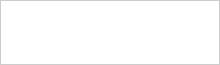それから約3年経った2014年2月、ナムサ村では再び識字教室が実施されていた。新たな教科書とノートを手に、同じメンバーの女性たちが夜間に集まっていた。新たな、とはいえ内容は文字の綴り方と簡単な計算という以前と同様の内容である。教室は、次第に参加者が集まらなくなり、数週間後には自然消滅という形で、3か月のカリキュラムを終えることなく終了した。
この識字教室は、ネパール政府教育省によるキャンペーンの一環であった[3]。教育省の傘下にあるノンフォーマル教育センターは、2012年から、「2015年までに非識字をなくす」ことを目的に、“Literate Nepal Mission”と表するキャンペーンをおこない、全国各地で識字教室を開催してきた。カブレ郡でも、1618教室が開催され、15歳から60歳までの約46,000人が対象となったと発表されている[4]。
識字教室における役割の違いと課題
このように一農村において、主催団体が入れ替わりながら幾度も識字教室がおこなわれることがある。事例からみるに、政府による識字教育キャンペーンは、全国的に一律に大規模に実施されることから、広域・量的に展開されるのに対して、NGOによるプログラムは、選択されたごく一部の農村を対象として小規模に質的に実施されるという特徴の違いがある。前者では、継続的な指導に限界があるのに対して、後者では、実施できる地域に限りがある点にむずかしさがある。しかし両者は、その活動範囲と持続性の点で相補的である。一方で、両者のあいだには、カリキュラムの進度の課題がある。すなわち、学習者の視点に立てば、主催団体が替わっても、相次いで同様のカリキュラムが繰り返されることになるのである。つまり、「क」(ka)「ख」(kha)「ग」(ga)… と、デーヴァナーガリー文字の綴り方を学習して一通りのカリキュラムが終わると、しばらくして次の団体が再び「क」「ख」「ग」の学習からはじめることになるのである。諸団体間の連携により、学習者にとってカリキュラムの進展性という点でより興味深い識字教育プログラムになるのではないかと考えられる。
教育省による広域的な識字教育キャンペーンが2015年で一段落を迎えようといういま、NGOによる活動が今後どのように展開されていくのか、注目していきたい。
それから約3年経った2014年2月、ナムサ村では再び識字教室が実施されていた。新たな教科書とノートを手に、同じメンバーの女性たちが夜間に集まっていた。新たな、とはいえ内容は文字の綴り方と簡単な計算という以前と同様の内容である。教室は、次第に参加者が集まらなくなり、数週間後には自然消滅という形で、3か月のカリキュラムを終えることなく終了した。
この識字教室は、ネパール政府教育省によるキャンペーンの一環であった[3]。教育省の傘下にあるノンフォーマル教育センターは、2012年から、「2015年までに非識字をなくす」ことを目的に、“Literate Nepal Mission”と表するキャンペーンをおこない、全国各地で識字教室を開催してきた。カブレ郡でも、1618教室が開催され、15歳から60歳までの約46,000人が対象となったと発表されている[4]。
識字教室における役割の違いと課題
このように一農村において、主催団体が入れ替わりながら幾度も識字教室がおこなわれることがある。事例からみるに、政府による識字教育キャンペーンは、全国的に一律に大規模に実施されることから、広域・量的に展開されるのに対して、NGOによるプログラムは、選択されたごく一部の農村を対象として小規模に質的に実施されるという特徴の違いがある。前者では、継続的な指導に限界があるのに対して、後者では、実施できる地域に限りがある点にむずかしさがある。しかし両者は、その活動範囲と持続性の点で相補的である。一方で、両者のあいだには、カリキュラムの進度の課題がある。すなわち、学習者の視点に立てば、主催団体が替わっても、相次いで同様のカリキュラムが繰り返されることになるのである。つまり、「क」(ka)「ख」(kha)「ग」(ga)… と、デーヴァナーガリー文字の綴り方を学習して一通りのカリキュラムが終わると、しばらくして次の団体が再び「क」「ख」「ग」の学習からはじめることになるのである。諸団体間の連携により、学習者にとってカリキュラムの進展性という点でより興味深い識字教育プログラムになるのではないかと考えられる。
教育省による広域的な識字教育キャンペーンが2015年で一段落を迎えようといういま、NGOによる活動が今後どのように展開されていくのか、注目していきたい。
註
[1] 1971年に出された国家教育システム計画(NESP: National Education System Plan)は、国内の学校制度を統合し、近代国家づくりの人的資源開発を目指すものであった。1977年には3年間の初等教育の授業料が無償化されている。81年になると、学校制度が変更されて初等教育が5年間になり、女子児童を含めて無料化された[畠2007: 97]。
[2] 識字教育プログラムの教材づくり、ラジオ放送プログラム、図書館建設、識字教育用教科書『ナヤゴレト』の発行などがおこなわれている[Shrestha 1977]。
[3] キャンペーンは、2000年にセネガルのダカールで採択されたダカール行動枠組みに対するネパール政府の対応としておこなわれた。
[4] 公式発表では登録者が参加したことになっているため、ノンフォーマル教育センターは、2015年9月現在で、92.5%の識字率を達成したと発表している。ただしナムサ村の事例のように、プログラム半ばで終了したり、実際は集まっていなかったという報告もあることから、公式発表の人数が実際に参加した人数とはならないと考えられる。
引用文献
Fujikura, Tatsuro. 2013. Discourses of Awareness. Martin Chautari.
畠博之. 2007. ネパールの被抑圧者集団の教育問題―タライ地方のダリットとエスニック・マイノリティ集団の学習阻害/促進要因をめぐって. 学文社.
Shrestha, Ramesh. 1977. Adult Literacy in Nepal. Institute of Nepal and Asian Studies of Tribhuvan University.